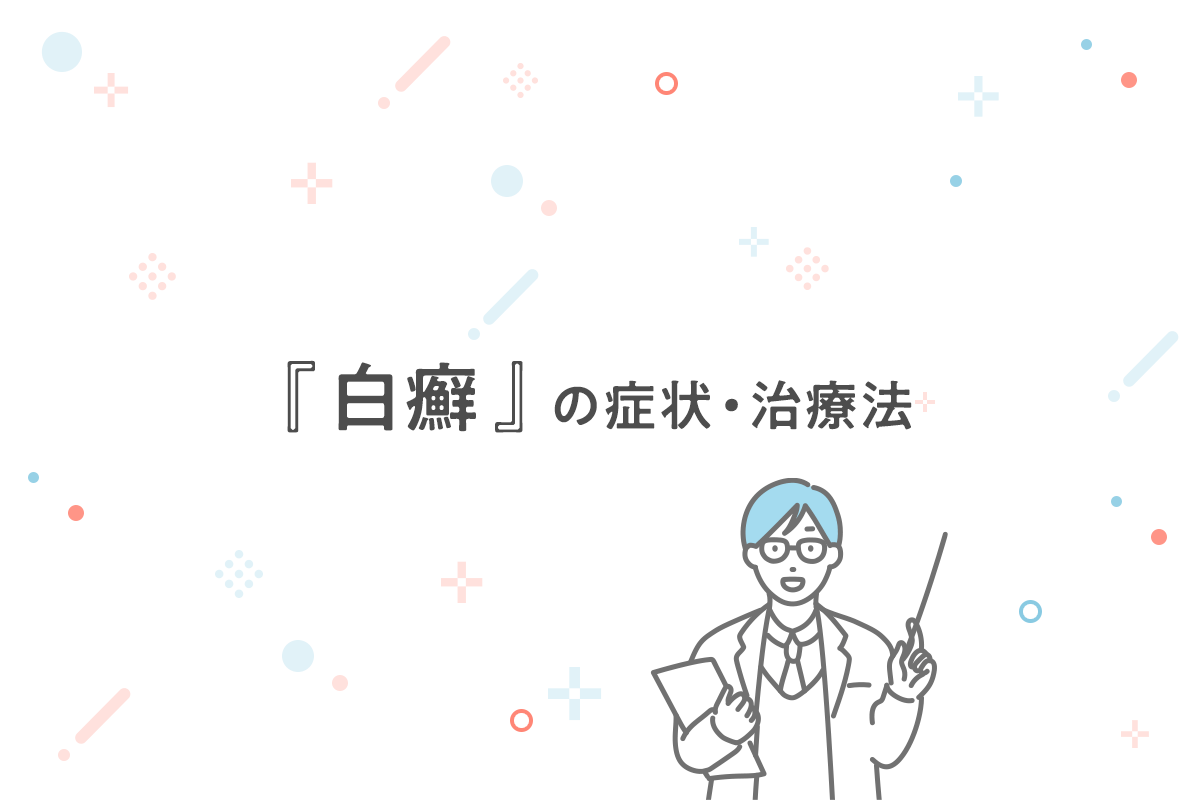「毎日のアルコール消毒で手が荒れてつらい…」、「指先の皮がめくれて痛い…」、そんな手のトラブルを抱えていませんか?感染症対策の意識が高まっている昨今、繰り返す手洗いやアルコール消毒によって手荒れに悩む人が増えています。
日々の感染症対策を続けながらも、健康的できれいな手を保つためには、これまで以上にしっかりケアをすることが必要です。
今回は、手洗いやアルコール消毒によって手が荒れる原因と予防法、手荒れが起きてしまった場合の正しいケア方法について解説します。
手荒れとは
手荒れとは、さまざまな外部刺激が原因で手や指の皮膚が水分を失って乾燥し、かゆみや赤みなどの炎症が起きる状態のことを指します。本来、健康な皮膚では、レンガの壁のように積み重なる「角質層」と、その隙間を埋めているセラミドなど細胞間脂質、さらに表面をコーティングしている「皮脂膜」が、外部からの刺激や異物の進入をしっかりブロックするとともに、皮膚の乾燥を防いでいます。これが“皮膚のバリア機能”です。
ところが、こすり洗いで角質層を傷つけたり、石鹸や洗剤で皮脂膜のコーティングまで除去してしまったりすると、皮膚のバリアが壊れ、そこからどんどん水分が抜けて皮膚が乾燥します。手荒れは、このように皮膚のバリア機能が低下し、外部からの刺激に対して無防備な状態になると起きやすい皮膚トラブルです。
手のひらは、私たちの身体の中でも特に皮脂の分泌量が少なく、その一方で、汗が出たり、乾燥したりすることがあります。特に手指は異物や薬品などの外部刺激に触る機会も多いため、皮膚のバリア機能が低下しやすい場所です。

手洗い・アルコール消毒での手荒れの原因
「手洗い・アルコール消毒」は感染症対策において重要視されています。しかし、その一方で、これらは皮膚のバリア機能を低下させ、手荒れの原因にもなります。
石鹸やハンドソープを使った手洗いでは、洗浄成分がウイルスや病原菌を除去するのに有効ですが、皮膚表面の皮脂膜まで洗い流してしまい、皮膚のバリア機能を低下させます。バリア機能が低下した状態では、皮膚の内部から水分が逃げだし、次第にカサカサと乾燥した状態になり、やがて手荒れを生じます。
石鹸と同様に、アルコール消毒にも、病原体を無効化する働きがあり、特に新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどのエンベロープ(脂質の外膜)を持つウイルスに対して力を発揮します。しかし、アルコールには強い脱脂作用(油脂を除去する力)があり、また、皮膚に付いたアルコールが揮発する時に、皮膚の水分を奪ってしまうため、ひどい乾燥状態を引き起こし、皮膚のバリア機能の低下を招きます。
バリア機能が正常でなくなった皮膚は、外部刺激に対して無防備かつ敏感になるため、石鹸やハンドソープの洗浄成分や、アルコール消毒そのものが新たな刺激になり、炎症が起きるという悪循環に陥ってしまいます。
手荒れの症状
手荒れは、手指の皮膚がカサカサして粉を吹くなどの症状から始まり、進行すると炎症が起き、「赤み・かゆみ」などの湿疹の症状が出現します。その他、部分的に皮膚がガサガサに硬くなる「角化(かっか)」や、皮膚がひび割れる「亀裂」などの症状が混在することもあります。手荒れは、正しいケアをせずに放置していると、慢性的な経過をたどりやすいため、注意が必要です。
手指にできる皮膚トラブルには、症状の特徴や原因によって病名がつけられているものもあります。なかには、手荒れと見分けがつきにくい皮膚の病気が隠れている場合や、医療機関で治療が必要な場合もあります。
- 手湿疹…手湿疹とは、その名のとおり手に出来る湿疹や炎症の総称です。赤みやかゆみ、ヒリヒリ感、小さなブツブツなどが混在して発症します。進行すると、ブツブツが破れてジュクジュクした傷になったり、慢性化すると患部がゴワゴワと硬くなったりすることもあります。バリア機能が低下した皮膚に、繰り返し石鹸や薬剤、アルコールなどの刺激が加わることで発症することが多いですが、なかにはアレルギーやアトピー性皮膚炎が関与して発症するタイプの手湿疹もあります。

水仕事による手湿疹の症例画像
症例画像を鮮明にする
※ボタンを押下することで症例画像が切り替わります。
- 汗疱・異汗性湿疹(かんぽう・いかんせいしっしん)…汗疱は中が透き通った1~2ミリの小さな水ぶくれ(汗疱)が、手のひらや足の裏に集中して現れる病気です。水ぶくれを無理やりむしったり、つぶさない限り、1か月ほどで自然によくなります。ただし、汗疱の患部に薬剤や摩擦などの刺激が加わると、接触皮膚炎を伴って周囲に広がり、強いかゆみと痛みを伴う「異汗性湿疹(いかんせいしっしん)」に進行することがあります。また異汗性湿疹と呼ばれるものの中には、金属へのアレルギー反応が関係していると考えられているものもあります。汗疱であれば、徐々に水ぶくれが吸収され、自然治癒しますが、再発を繰り返すことが多いです。
- 掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)…中に膿が溜まったブツブツ(膿疱)が手のひらや足の裏にたくさんでき、よくなったり、悪くなったりを繰り返します。中年やヘビースモーカーの方に多く見られ、発症には喫煙や金属アレルギー、虫歯、扁桃腺炎、副鼻腔炎などの細菌感染が関係しているという説がありますが、分からないことも多い病気です。
- 白癬(はくせん)…いわゆる水虫と呼ばれるものです。一見、ただの手荒れと症状がよく似ていますが、白癬菌(はくせんきん)というカビが繁殖して発生する皮膚の病気で、ほとんどが足白癬(水虫)を合併しています。手にできるものは「手白癬(てはくせん)」と言います。白癬になると皮膚が赤くなってジュクジュクし、やがて皮がむけることもありますが、手のひらや手指全体がゴワゴワと硬くなることが多いです。皮膚科では、患部の皮膚を採取して、顕微鏡でカビの有無を調べることで白癬かどうかを判断します。手白癬になると自然治癒することはなく、人にうつる病気なので、病院を受診しましょう。

手の水虫(手白癬)
症例画像を鮮明にする
※ボタンを押下することで症例画像が切り替わります。
手洗いとアルコール消毒はどちらもするべき?
「手洗い・アルコール消毒」は、感染症対策に有効である一方で、使い続けると皮膚にとっては大きなダメージになります。特に、アルコール消毒は、その特性上、手荒れを引き起こしやすく、日常的な連用には注意が必要です。
家庭やオフィスなどで普段行っている感染症対策を見直しましょう。石鹸で手洗いをした後、さらにアルコール消毒をしていませんか?
実は、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの病原体を除去する効果は、石鹸もアルコールも同等であることが科学的に検証済みであり、「石鹸による手洗い」のみで十分な効果があることが分かっています。そのため、手洗いのあと、さらにアルコール消毒をする必要はありません。
さらに石鹸による手洗いは、ノロウイルスなど、アルコール消毒では除去できないウイルスに対しても一定の効果を発揮します。
ちなみに厚生労働省や国立感染症研究所のウェブサイトでも、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどに対しては
- 石鹸による手洗いのあと、アルコール消毒は不要
- 流水で手洗いができない場合には、アルコール消毒を使用しましょう
と情報発信しています。
これらの情報を元に、家庭やオフィスなど、水が使える場面では、アルコール消毒は使わずに、基本的に石鹸による手洗いを行うようにし、皮膚の健康を守りながら、より少ないダメージで感染症対策を続けるのがよいでしょう。
そして、皮膚への負担の大きいアルコール消毒は、外出先など水が使えない時の使用にとどめましょう。アルコール消毒を使用する場合は、厚生労働省が推奨するアルコール濃度70%以上のものを選ぶようにしてください。
また、アルコール消毒は使用方法にもコツがあります。アルコール消毒は、手全体にさっと塗るだけでは不十分で、15~30秒ぐらいかけて手全体にしっかり擦り込む必要があります。消毒液が少なすぎたり、指先のみにつけたりする方法では、十分な効果が得られないので注意が必要です。
手荒れの予防・ケア方法
手洗いやアルコール消毒を続けていると、手荒れはつきものです。手荒れの予防方法や、正しいケアの方法を知っておきましょう。
手荒れを予防するには
手荒れを防ぐために大切なのは、「バリア機能を低下させてしまう習慣を避ける」ことです。
- 肌に直接触れる石鹸やハンドソープは、洗浄力の強いものを避け、皮脂の喪失を防ぐ。
- 手を洗う時は、角質層を傷つけないように、泡でつつむようにやさしく洗う。
- 水仕事の際は、ゴム手袋を使用して皮脂を守る。
- ゴム手袋でかぶれることもあるので、なるべく木綿の手袋をしてその上からゴム手袋をする。
などの工夫をし、肌のバリア機能を守りましょう。ただし、ゴム手袋は蒸れやすく、長時間着用しているとかゆみが強くなることがあるので、短時間の使用にとどめておきましょう。
手荒れのケア方法
手が何となくカサカサしている程度の手荒れであれば、ワセリンなどの軟膏基剤の保湿剤でこまめにケアし、皮脂・水分を逃がさないようにすることで、ほとんどの場合は自然に回復します。
角質の一部が乾燥して硬くなっている(角化)部位には、角質をやわらかくする尿素配合クリームを使用するとよいのですが、ゴシゴシ擦ることは厳禁です。
- 入浴や水仕事の後は、清潔なタオルで軽く水分を拭き取ってから、完全に乾ききらないうちにワセリンなどの軟膏基剤の保湿剤を塗って保湿する。
- 乾燥が気になったら、こまめにワセリンなどの軟膏基剤の保湿剤で保湿する。
- 乾燥しやすい季節には、手袋を着用する。
などの工夫をし、皮膚のうるおいを逃がさないようにケアを習慣づけましょう。
一方、手湿疹のように、「赤み、ヒリヒリ感、ブツブツ」などの症状がある場合は、手荒れが進行して、皮膚が炎症を起こしているサイン。このような症状が出ている場合は、保湿ケアだけでは回復が難しく、ステロイド軟膏で炎症を抑える治療が必要です。手指は角質層が比較的厚いため、強めのステロイド軟膏を使ってすみやかに症状を抑えましょう。
炎症が治まり、皮膚が正常な状態へと一旦回復したら、ワセリンなどの軟膏基剤の保湿剤によるスキンケアを習慣づけ、皮膚のバリア機能を正常に保つことが大切です。
ただし、手の甲や指の関節部分などにひび割れや傷ができた時、出血している箇所に関しては、抗菌剤を塗って治療するなど、部位ごとに治療薬を使い分ける必要があります。
炎症が起きている部位に対して、十分な強さのステロイド軟膏を1週間使用しても、症状が改善しない、あるいは悪化している場合は、単なる手荒れではなく、「汗疱・異汗性湿疹」や、「掌蹠膿疱症」、「白癬」など、医療機関での治療を要する病気である可能性があります。症状が長引く場合は、自己判断せず、専門医を受診しましょう。
監修

帝京大学医学部皮膚科 名誉教授
渡辺晋一先生
1952年生まれ、山梨県出身。アトピー性皮膚炎治療・皮膚真菌症研究のスペシャリスト。その他湿疹・皮膚炎群や感染症、膠原病、良性・悪性腫瘍などにも詳しい。東京大学医学部卒業後、同大皮膚科医局長などを務め、85年より米国ハーバード大マサチューセッツ総合病院皮膚科へ留学。98年、帝京大学医学部皮膚科主任教授。2017年、帝京大学名誉教授。帝京大学医真菌研究センター特任教授。2019年、『学会では教えてくれない アトピー性皮膚炎の正しい治療法(日本医事新報社)』、2022年『間違いだらけのアトピー性皮膚炎診療(文光社)』を執筆。